梅崎 仁JIN UMEZAKI
食料第一・第二本部
畜産部
法学部 | 1998年卒
※所属部署は取材当時のものです
MY CAREER
- 1998年
- 食料経理部で経理・リスクマネジメント業務
- 2001年
- 畜産部
- 2002年
- 豪州 Rangers Valley駐在
- 2003年
- 水産・畜産部 Rangers Valleyのトレード担当
- 2015年
- 丸紅米国会社 オマハ支店長
- 2016年
- 米国シカゴ 関連会社牛肉生産工場駐在
- 2017年
- 米国カンザス Creekstone Farms Premium Beef駐在
- 2019年
- 畜産部 畜産二課長
丸紅に入社を決めた理由を教えて下さい
私が就職活動をしていたのは、就職氷河期と言われた時代であり、メーカーや金融、商社など、幅広い業界・業種にアプローチしました。その中で丸紅は、最も自分とフィーリングがあった企業でした。採用担当者をはじめ、接した社員たちが温かく、気さくな雰囲気で、OB訪問や面接でも一番フランクに正直に自分の思いを話すことができました。当時は、総合商社という舞台で何をやりたいかを明確に持っていた訳ではありませんが、丸紅は若いうちからチャレンジする機会があると感じて入社を決めました。

現在どのようなお仕事をされていますか?
現在、私は豚肉、鶏肉、加工品のトレードを扱う畜産第二課をマネジメントする立場です。年々変化していく畜産業界において、旧来型のトレードビジネスだけで生き残ることはできません。求められる新たな商社の役割・機能を見出し、ビジネスモデルを進化させていくことが私のミッションです。

具体的な取り組み内容を教えて下さい
一つは、鶏肉生産事業のバリューチェーン統合及び最適化です。鶏の肥育場から、工場での加工、それら加工品が消費者に届くまでを、イニシアティブを取って一貫して管理する仕組みを構築しています。子会社や世界各地にある生産拠点を軸として、メーカー機能まで深く踏み込むことで、顧客のニーズを捉えて最適な商品を戦略的に市場に送り出すことができるようになります。
もう一つは、「スペシャリティ商品」です。これは、他社と圧倒的に差別化を図ることができる商品のことを指します。丸紅は米国、豪州の子会社で、牛肉の品質管理体制を整え、高品質な商品の生産に徹底的に向き合っています。ここで培ったノウハウを国内外の生産拠点に展開し、スペシャリティ商品の開発を推し進めていきます。

ターニングポイントとなった経験を教えて下さい
丸紅の出資先が投資する米国シカゴの牛肉生産工場で、経営再建に取り組んだことです。当時の私にとって工場の経営は全く未知の世界。不安だらけでのスタートでした。まず驚いたのは、年間予算が無かったことです。数週間先までの予算管理しかしていない。牛肉の価格は相場により変動するから予算を策定する意味が無いというのがその理由でしたが、会社経営においてはありえません。これでは経営再建はできないと、年間予算の策定から着手しました。
また、生産ラインにいる現場スタッフとのコミュニケーションを強化しました。それまでの経営者はマネジメント層とのコミュニケーションは行っていましたが、本当の改善のヒントは現場にあると考えたからです。といっても難しいことをした訳ではありません。お菓子を食べながら打合せをしたり、クリスマスに社員に牛肉をプレゼントしたり。そうしているうちに、だんだんみんなが現場の問題点を話してくれるようになったんです。経営層が考えていることも浸透し、社員の意識改革ができて、顔つきが変わってきた。最終的に完全に経営再建できたとまでは言えないのですが、私の大きな成功体験です。赴任前は、さまざまな経営指標を使った再建計画を思い描いていたのですが、現場を見てそんなことじゃない、と考えをすぐに切り替えられたことが勝因だったと思います。
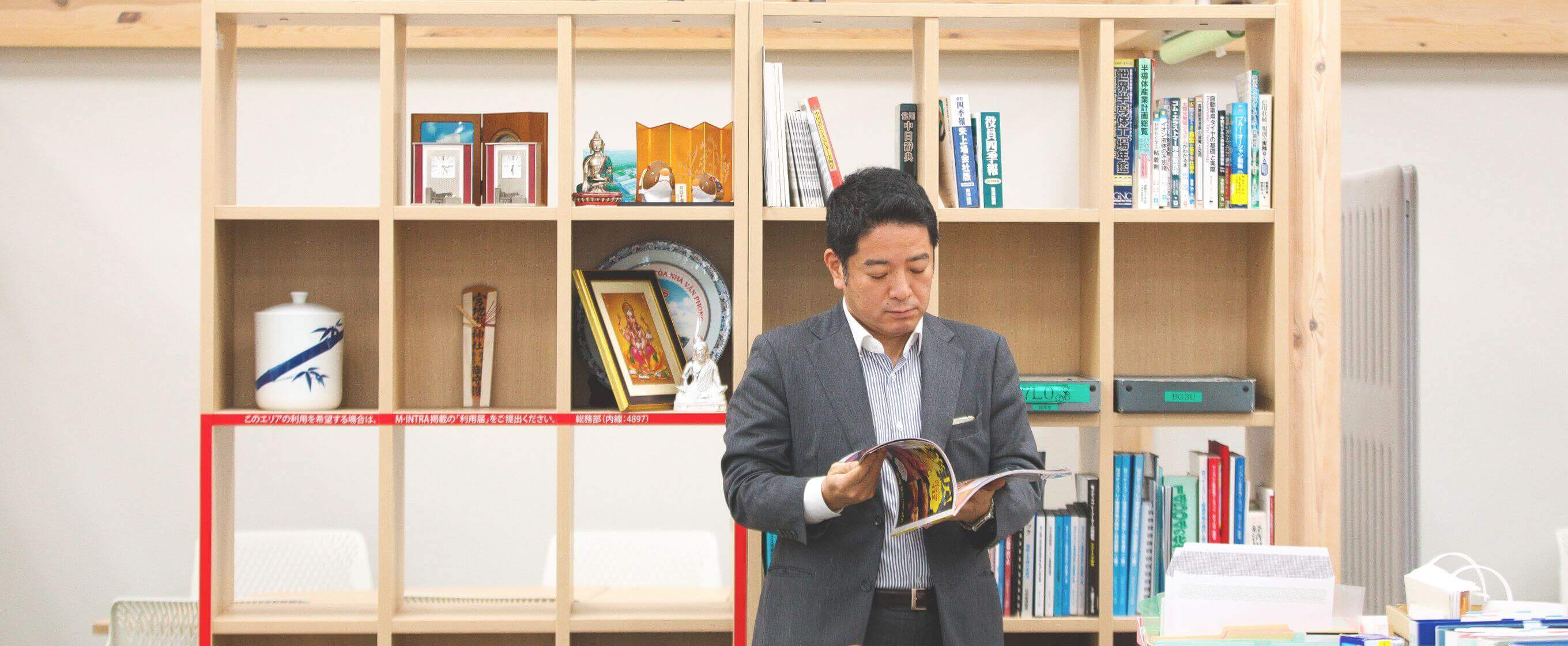
丸紅の一員として、
あなたが大切にしているポリシーは?
徹底した「現場主義」。それが私のこれからも変わらないポリシーです。たとえば商品に問題が発生したとき、通常であればサプライヤーに報告して対応を任せるのが従来型のやり方であり、ある意味では効率的な方法です。でも私は工場に直接行って何が起こっているのかを自分の目で確かめ、現場の人たちと話して解決策を一緒に考えたい。全体を俯瞰しながら現場に深く入り込んで仕事をする。商社で働く醍醐味はここにあると思います。
After Work
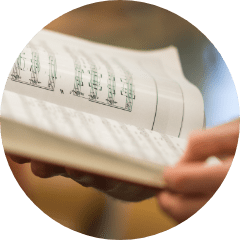
年末には毎年各所でベートーヴェン作曲の交響曲第九番「合唱」が演奏されますが、中でも有名なのが大阪城ホールで開催される「1万人の第九」。私は、一般公募により都度結成される合唱団に、過去4度参加しています。1万人での合唱は、大勢で声をあわせ一体となって歌う楽しさや喜びに加え、1年を振り返る特別な時間です。

